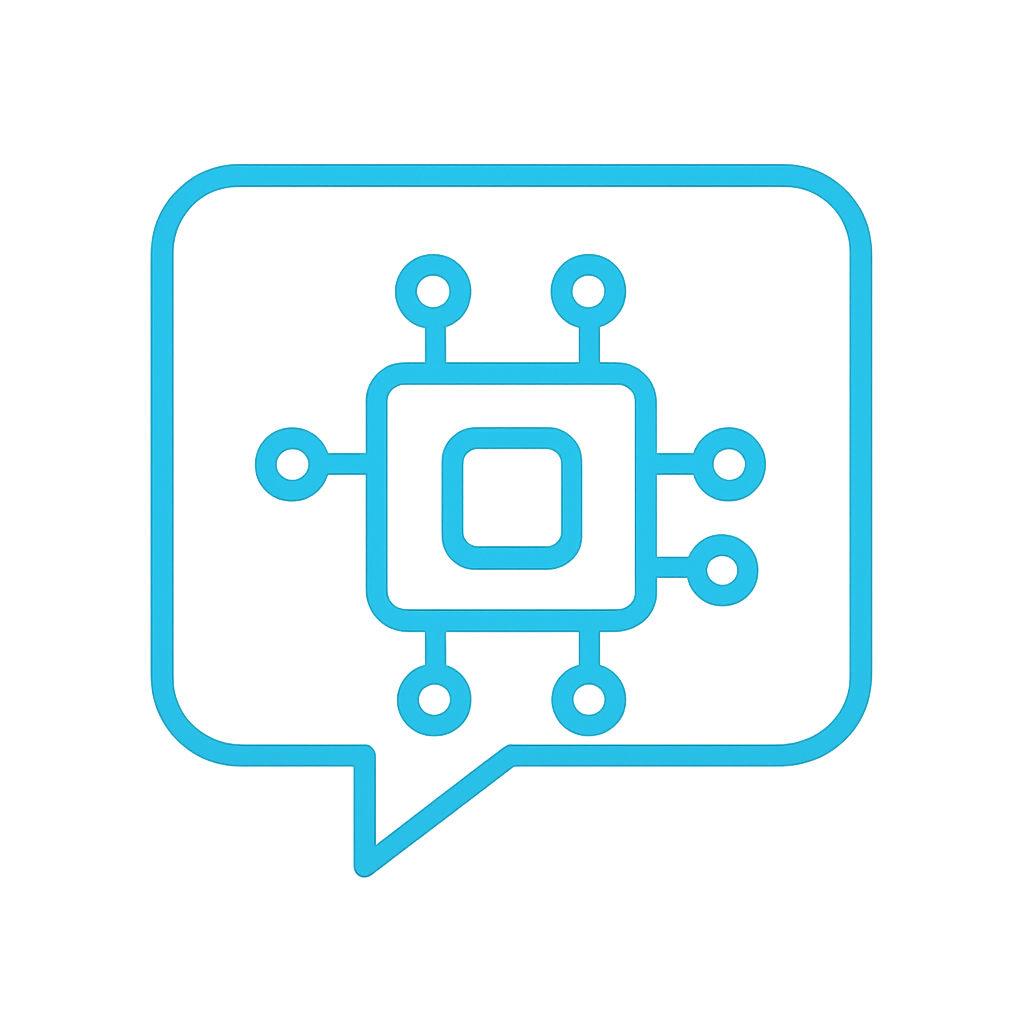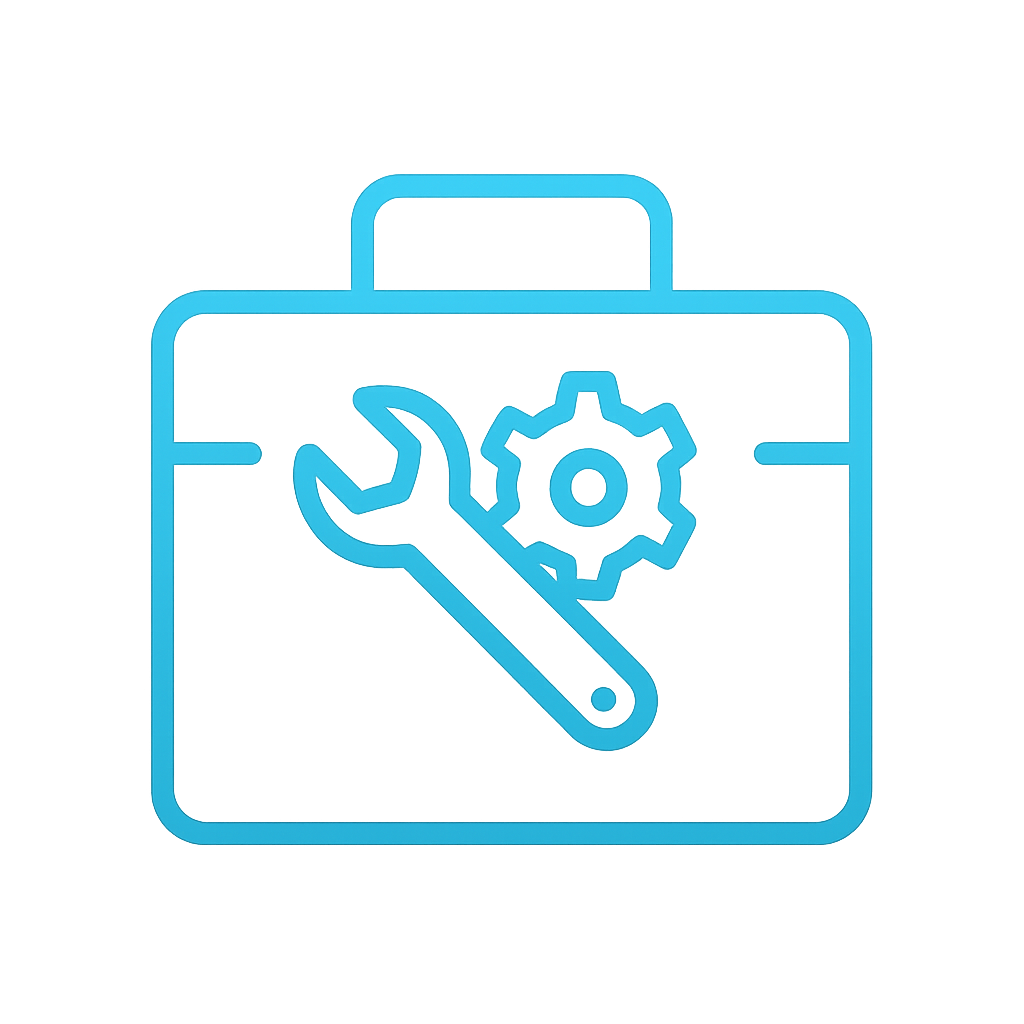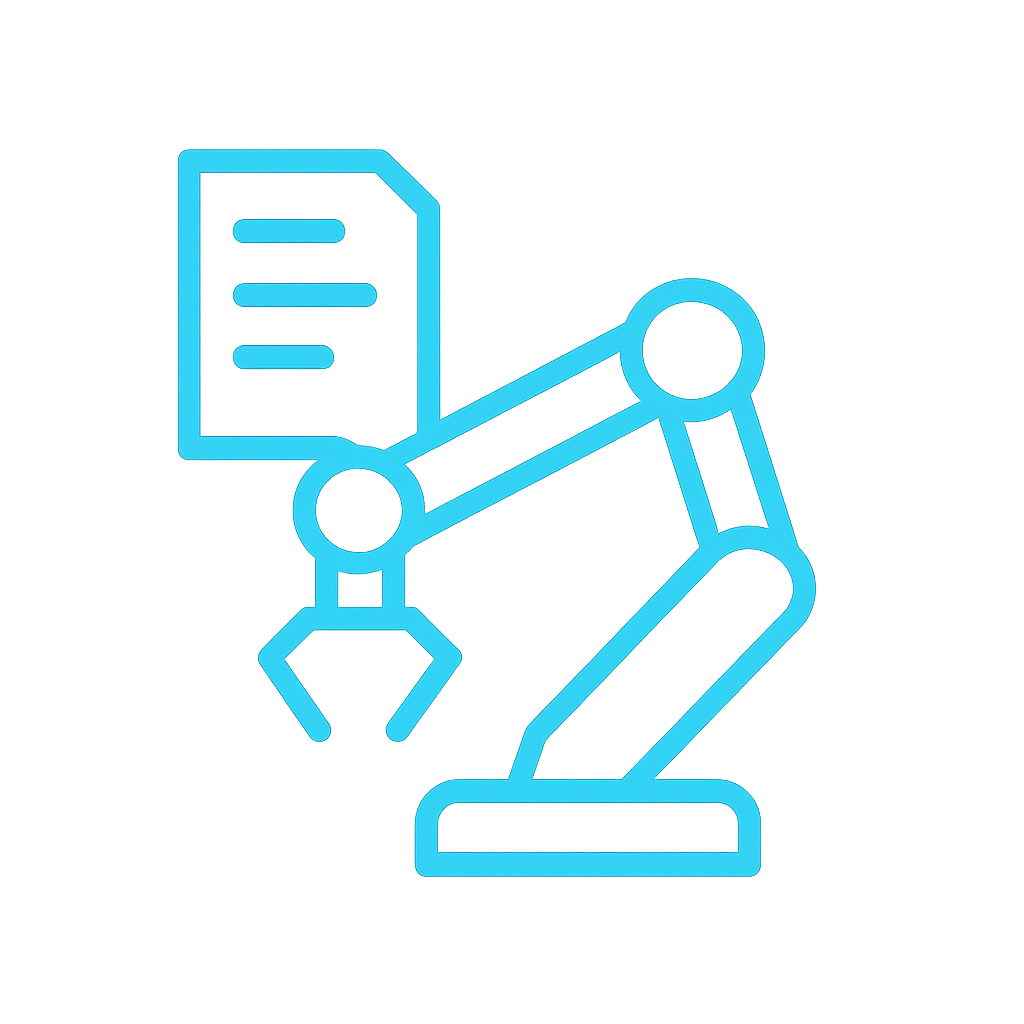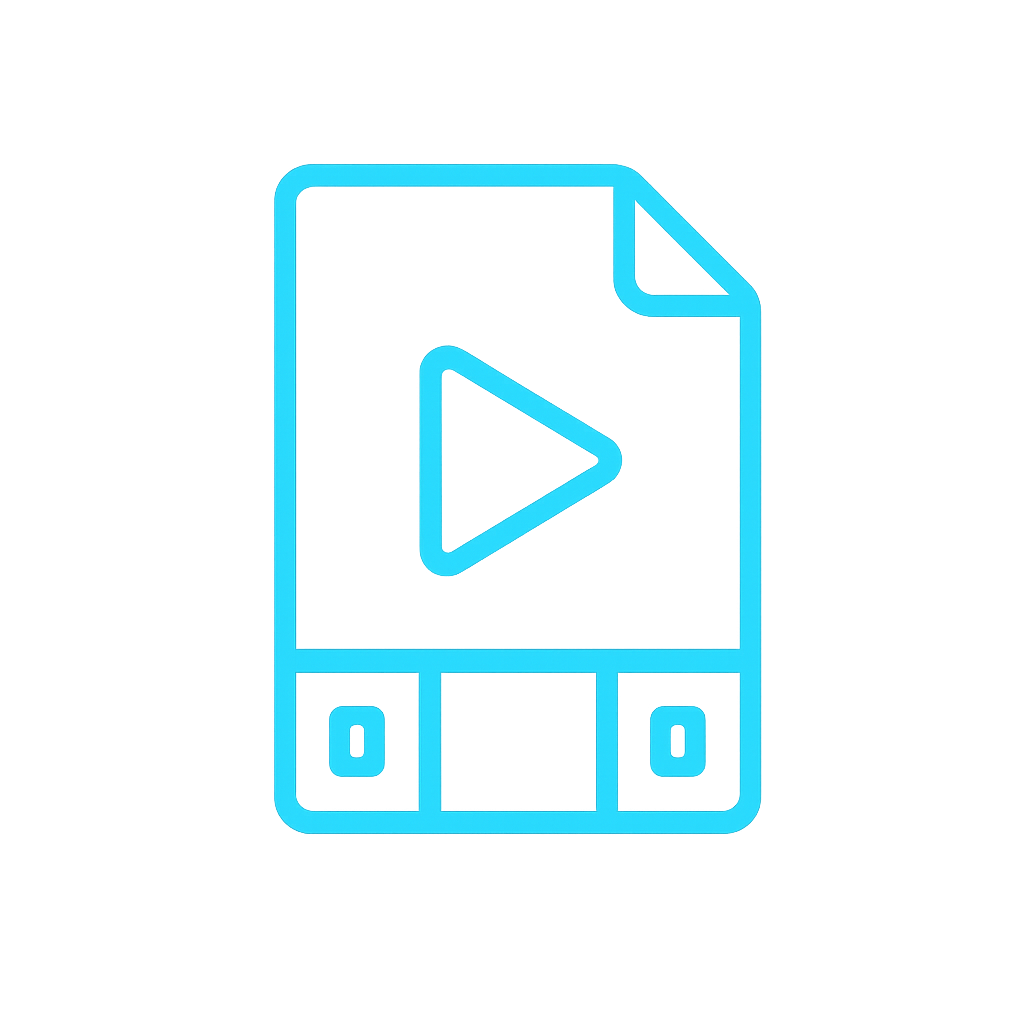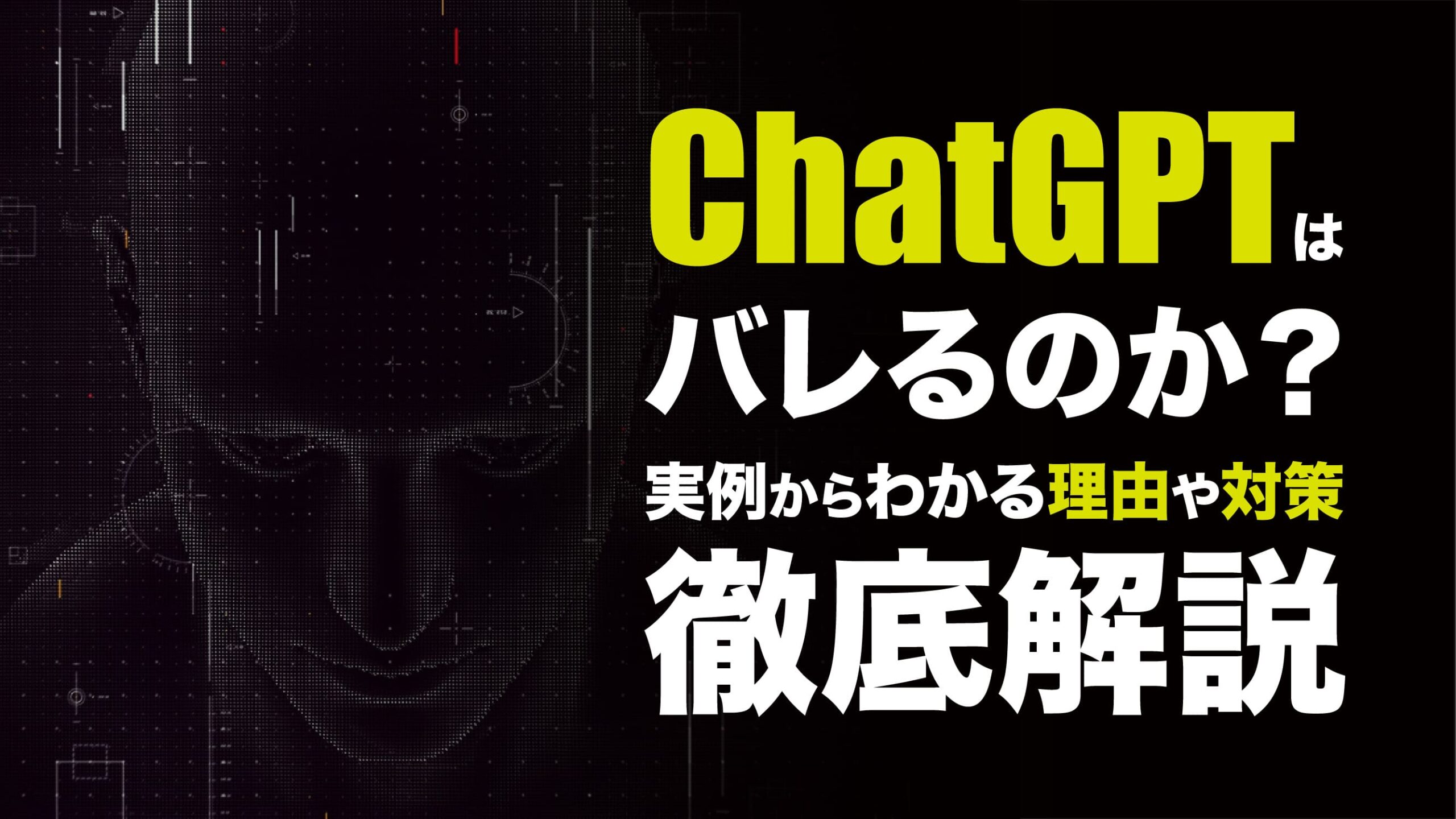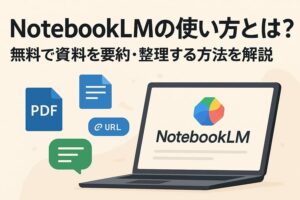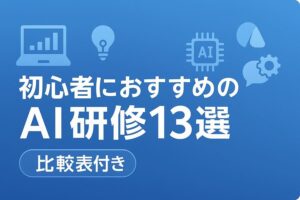ChatGPTで作成した文章は、じつは高い確率で見破られています。
教育機関や企業でAI検出ツールの導入が急速に進んでいる一方、不正使用による処分事例も増加しています。
そういった状況の中、以下のような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
- ChatGPTで書いた文章が本当にバレるのか知りたい
- どのような場面でAI使用が発覚しているのか気になる
- バレないように使う方法があるなら知りたい
結論から言うと、ChatGPTで生成した文章は特徴があるため、検出ツールや人の目によって見破られる可能性があります。
しかし、適切な使い方を理解すれば、咎められるリスクを軽減することも可能です。
今回は、実際にChatGPT使用がバレた事例から、AI文章の特徴、適切な活用方法まで詳しく解説します。
AI利用を見破られることに不安を感じている方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。

ChatGPTがバレた5つの実例とその理由

ここでは、ChatGPTの使用が疑われたり発覚したりした以下5つの事例を取り上げ、なぜバレたのかを解説します。
- 読書感想文|子供らしくない大人びた表現に違和感
- 就活ES|面接の食い違いで発覚
- 卒論・レポート|TurnitinによるAI検出で疑義対象に
- 法的書類|AIが作成した架空の事件引用を含んで提出
1. 読書感想文|子供らしくない大人びた表現に違和感
2023年、ある小学校で読書感想文の課題において、ChatGPT使用が発覚する事例が発生しました。
小学5年生の生徒が提出した感想文に「感銘を受ける」「絆を再確認する」といった本人らしからぬ表現が含まれていたため、教員は違和感を覚えたとのこと。
そこで教員が本人に確認したところ、ChatGPTが書いたと答えています。
その後、教員は生徒たちとともにChatGPTとの向き合い方を考え、人間とAIの良さを活かした作文を書く授業を実施したそうです。(参考:FNNプライムオンライン)
このように学生がChatGPTを使ってバレた話は、Yahoo!知恵袋などでも多数確認できます。
2. 就職活動|AIによる履歴書は見抜かれている
就職活動のエントリーシートや履歴書をAIに任せた場合、見抜かれている確率は高いと考えたほうがよいでしょう。
現に、アプリ自動化企業Zapier社の採用担当者は「応募の25%ほどはAI生成で作成したように見える」と語ったとのこと。
実際に面接まで進むと、矛盾した回答をしたり本人の言葉で話せなかったりするケースもあるようです。
ただし、AIを使っていたとしても、書き始めのヒント出しや構成の整理のような補助的な活用であれば効果的だと考えるポジティブな見方もあります。
3. 卒論・レポート|TurnitinによるAI検出で疑義対象に
大学に提出する卒業論文やレポートが、AI検出ツールによって疑義対象とされるケースが増加しています。
2023年から登場した判定ツールTurnitinの例では、世界の学生論文 2,200万件以上を解析した結果、約11%がAI文章を2割以上含んでいる可能性があると判定されました。
さらに、そのうちの3%は8割以上をAIで生成していると判断されています。(参考:WIRED)
当時のTurnitinは英語によるレポートが主な対象でしたが、2025年に入ってから日本語の提出物に対応した機能も発表されました。(参考:Turnitin)
こうしたAI検出ツールを導入している学校では、AI文章がバレる確率が高くなるでしょう。
4. 法的書類|AIが作成した架空の事件引用を含んで提出
2023年6月、ChatGPTが出力した架空の事件引用6件を含めた法的準備書面を提出した弁護士2名が制裁を受ける事件が発生しました。
弁護士が書面を提出した際、相手方の弁護士が判例を確認できなかったため裁判所に報告し、調査した結果虚偽であったと判明したとのことです。
意図的ではなかったものの専門職としての調査義務を怠ったとして、総額5,000ドルの制裁金が課されることに。(参考:Reuters)
この事件をきっかけに、法曹界ではAIによる引用は複数のデータベースで確認すべきとの意識が広がっています。
AI文章と判断されやすい7つの特徴

ここでは、AI文章と判断される可能性が高くなる7つの特徴を整理します。
- 抽象的な導入文で始まる
- 主語と述語の対応が正確すぎる
- 文体が終始「ですます」で揺れがない
- 具体的な経験や感情の描写がほとんどない
- 同じ構文の繰り返しが目立つ
- 表現のバリエーションに乏しい
- 読み手を意識した工夫や個性が見られない
人間の文章でも上記の特徴があるとAIと誤解されかねないので注意しましょう。
1. 抽象的な導入文で始まる
AI生成文章の最大の特徴は、定義や一般論から始まる抽象的な導入文です。
人間が書く文章では、具体的なエピソードや疑問文から始まることが自然ですが、AIは安全かつ無難な導入を選びます。
以下の表は、人間とAIの書き出し方を比較した例です。
| 書き手 | 書き出しの例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 人間 | 「昨日、 コンビニでレジ袋を断ったとき、 ふと環境問題について考えた」 | 具体的な体験から始まる |
| AI | 「環境問題は21世紀における最重要課題の一つである」 | 抽象的な定義から始まる |
| 人間 | 「なぜプラスチックごみは減らないのだろうか?」 | 疑問形で読者の関心を引く |
| AI | 「プラスチック汚染について論じる」 | 形式的な宣言で始まる |
読み手は、このような抽象的で人間味の薄い導入文に違和感を覚えやすくなります。
2. 主語と述語の対応が正確すぎる
ChatGPTが生成する文章は、文法的に完璧すぎることが特徴です。
人間が書く文章には、話し言葉のように省略したり、あえて崩した表現にしたりするといった「ゆらぎ」があります。
しかし、AIは常に主語と述語を明確にし、教科書のような正しい文法を出力する傾向があります。
- AIの書き方:私は昨日、友人と会って、楽しい時間を過ごしました
- 人間の書き方:昨日友人と会って、楽しく過ごした
文法的に正しい表現も、度が過ぎれば不自然さを生む要因の一つです。
3. 文体が終始「ですます」で揺れがない
AIの出力する文章は、文体の一貫性が異常に高いです。
最初から最後まで同様の丁寧語で統一され、文体の揺れがまったくありません。
人間が書く文章では、話している内容によって語尾が切り替わったり、強調したい部分で体言止めを使ったりすることもあるでしょう。
「〜です」「〜ます」といった文末表現が機械的に繰り返されていれば、人が書いていない印象が一層強まるのです。
4. 具体的な経験や感情の描写がほとんどない
ChatGPTが生成した文章には、個人的な体験談や具体的な感情の描写が欠けています。
「〜と感じました」といった表現はするものの、感情の大きさが伝わるような描写に乏しいです。
人間の表現では、以下の表のように感情の動きや状況などを含めるので、感情の大きさや深さが伝わりやすいです。
| 感情 | AI の表現 | 人間の表現 |
|---|---|---|
| 喜び | 「とても嬉しく思いました」 | 「飛び上がりたいほど嬉しくて、 思わず母に電話してしまった」 |
| 悲しみ | 「悲しい出来事でした」 | 「胸が締め付けられるような痛みを感じ、 何も手につかなかった」 |
| 驚き | 「驚きました」 | 「えっ?と声が出て、 しばらく状況が理解できなかった」 |
| 怒り | 「怒りを感じました」 | 「カッとなって、 握りしめた拳が震えていた」 |
また、AIは体験することができないため、人から聞いた情報でしか物事を伝えられません。
細部まで伝えられない感情や体験談では読み手に共感を与えにくく、文章全体が他人事のように感じられてしまうでしょう。
5. 同じ構文の繰り返しが目立つ
AIによる文章には、特定の構文パターンをくりかえし使用する傾向があります。
ときには「〜は〜します。」のようなパターンだけで、単調な長い文章を書いてしまいます。
ブログ記事などを書く際は「まず」「次に」「そして」などの順で構成された見出しを同じように次々と出力することも。
同じパターンを延々とくりかえしていれば、簡単にAIだと見破られて当然です。
6. 表現のバリエーションに乏しい
ChatGPTは標準的な単語を選びやすく、表現のバリエーションがないという欠点を抱えています。
特に以下のような単語はAIが好んで使うことが多いです。
- 重要
- 効果的
- 最適
- 実現
- 活用
また、人間であれば「麗しい」「見目麗しい」「眩い」などのバリエーションで表現できるところを、AIは「美しい」のように汎用的な単語になりがちです。
比喩も「まるで〜のような」といった直接的な表現に留まり、独特な表現方法は期待できません。
特に長い文章であれば、人間らしくない表現に気付きやすくなるでしょう。
7. 読み手を意識した工夫や個性が見られない
読者を引き込む工夫や書き手の個性は、AIの苦手分野の一つです。
人間が書く文章には以下のような文体や語彙選択、リズムなどが含まれており、書き手の人柄や考え方が伝わってきます。
- 「〜って思いませんか?」のような問いかけ
- 「じつは〜」という意外性の演出
- 「(笑)」や「!」での感情表現
- 方言などの特徴的な言い回し
- 個人に向けた直接的な呼びかけ
AIにはこれらの要素がほとんど見られず、予測しやすい文章になりやすいです。
ChatGPT利用がバレにくい対策方法5つ

ChatGPTを活用しながらも、AI使用を疑われないための対策方法があります。
ここでは、リスクを軽減できる以下の5つの方法を解説していきます。
- 生成文をそのまま使わず自分の言葉に書き直す
- 出典や参考文献をきちんと記載する
- 確かな情報であるか調査する
- 要約や下書きに限定して活用する
- 利用が許可された範囲内で使用する
1. 生成文をそのまま使わず自分の言葉に書き直す
ChatGPTの出力をそのまま使用せず、自分の言葉で書き直しましょう。
人の手で書き直さない文章は、検出ツールにも引っかかりやすくなり危険です。
書き直す際は、同義語に変えたり語順を入れ替えたりするような小手先の修正では不十分でしょう。
出力された文章を熟読し、かみ砕いた自分なりの解釈に書き換えるのがおすすめです。
以下のような要素を追加すると、より人間らしい文章になります。
| 要素 | 例 |
|---|---|
| 情報の深掘り | 説明が不十分な箇所の情報量を増やす |
| 具体例や体験談の追加 | イメージしやすい具体例や実体験を追加する |
| 感情の付与 | 自分の感想や意見を付け足す |
| 文末表現や文体の変更 | 体言止めや疑問文を混ぜて単調さをなくす |
| 個性的な表現 | 自分らしい言い回しに変更する |
2. 出典や参考文献をきちんと記載する
AIで出力した文章にデータが含まれている場合は、信頼できる出典を必ず追加してください。
仮に文章がAIのように感じられても、正しい出典元を記載することで信頼性を得られる可能性があります。
出典元を探すときは、政府や公式からの一次情報から調べるのが鉄則です。
以下のようなサイトや書籍を出典元として信頼性を高めましょう。
| 情報の種類 | 推奨される出典の例 |
|---|---|
| 統計データ | e-Stat(政府統計) |
| 専門知識 | 政府機関、 関連する専門機関、 学術論文 |
| ニュース | 新聞社のデータベース、 ニュースサイトの記事、 公式サイトの発表 |
| 一般常識 | 辞書、 百科事典 |
一次情報を見つけられず個人ブログなどから引用する際も、出典の掲載は忘れずに。
3. 確かな情報であるか調査する
ChatGPTの生成文に書かれている情報は必ずファクトチェック(事実確認)してください。
もしAIが勝手に作った存在しないニュースや事例をそのまま提出すると、信頼性を問われる事態になりかねません。
特に以下のような情報が間違って出力されやすいため、複数の信頼できる情報源で検証してください。
- 日付
- 統計データ
- 専門的な内容
- 公開または更新されたばかりの情報
ファクトチェックの対象が多いときは、事実の確認に特化している以下のようなツールを利用してみるとよいでしょう。
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| iWeaver AIファクトチェックツール | 文章を貼り付けてAIが自動判定するツール |
| Felo 事実確認エージェント | AIが複数ソースを横断検索するツール |
| Genspark ファクトチェック | 情報をクロスチェックして要約するツール |
| Google Fact Check Tools | 既存の検証記事を検索できるデータベース |
4. 要約や下書きに限定して活用する
ChatGPTを文章生成ツールではなく、要約や下書きを作るツールとして活用する方法がおすすめです。
出力された要点を自分の言葉で書くことで、オリジナリティのある文章を自然と書けるはずです。
利用する場面を以下のようなシーンに限定し、バレるリスクを減らしましょう。
| 活用シーン | 具体的な使い方 |
|---|---|
| ブレインストーミング | アイデア出しの段階でChatGPTに「案を10個挙げて」と依頼し、 その中から自分なりの視点で3つを選び深堀りする |
| 構成・見出しの作成 | 記事や論文の構成を考える際にChatGPTで基本的な流れを生成し、 それを土台に自分の論点を追加する |
| 参考論文の要約 | ChatGPTで論文の要点を把握し、 重要な部分を参考にする |
| 言語の翻訳 | 英語の専門用語を日本語で理解したいときに、 ChatGPTで概念の説明を受ける |
| 文法チェック | 自分で書いた文章の文法的な誤りをChatGPTで確認し、 修正案を参考にする |
ポイントは、出力された内容をすべて取り入れるのではなく、自分の考えと照らし合わせて取捨選択することです。
AIにすべてを任せない使い方で、オリジナリティを保ちながら効率的に作業を進めてください。
5. 利用が許可された範囲内で使用する
仮にバレたとしても問題とならない範囲でChatGPTを使うのが一番の対策方法です。
たとえば大学では、以下のような使い方が認められているケースが見られます。
- 英語の文法チェック
- アイデア出し
- プログラミングのレビューやデバッグ
- 文献の検索キーワード案を生成
ただ、実際に使えるかどうかは学校によって異なり、場合によっては一切の使用が禁じられていることも。
学校や企業のガイドラインを確認し、許可された使い方のみに留めましょう。
企業での利用は制限事項に注意
企業においては、以下のような理由でAIの利用を制限していることが多いです。
- 個人情報の保護
- 誤った内容の出力
- 企業秘密の保護
- 著作権などの権利侵害
- 法的責任の明確化
いずれの理由も企業の信頼性に繋がっており、AI利用がバレれば大きな問題に発展する可能性があります。
ChatGPTを利用したほうが効率が良いとしても、企業ではどこまで許容されるかを明確にしてから使うべきです。
ChatGPTがバレることに関するFAQ

ChatGPTの利用に関する、よくある質問と回答を紹介します。
- ChatGPTの文章はどのようにしてバレるのですか?
- コードや翻訳文もバレることがありますか?
- OpenAIに履歴が残って会社にバレることはありますか?
- SPIや課題に使ったら処分されますか?
- どのような検出ツールがあるのですか?
- AIを使ったのがバレたら不利になりますか?
- ChatGPTの文章はどのようにしてバレるのですか?
-
AI検出ツールと人の目の両方でバレる可能性があります。
検出ツールがチェックするのは、文章の予測しやすさや文の長さのばらつきです。
文法が完璧すぎたり、個人的な体験が書かれていなかったりする文章は、経験豊富な人の目によって疑われます。
また、こうしたツールや経験以外にも、ChatGPTを使ったことが明らかになるさまざまな手法が考案されています。
その一例となるのが、参考とする課題文に白い隠し文字を含めてChatGPTに不自然な文字を出力させる手法(トロイの木馬)です。
参考:Newsweek(英文)
- コードや翻訳文もバレることがありますか?
-
はい、バレる可能性があります。
ChatGPTが出力するプログラミングコードは、GitHubなどにある既存のコードとそっくりなことが多いため、ツールなどを利用してすぐに見つかってしまいます。
翻訳文は直訳すぎて不自然な日本語になっていることが多いです。
仮にすぐバレなかったとしても、コードや翻訳文の内容を把握していなければ、質問に答えられず疑われてしまうでしょう。
- OpenAIに履歴が残って会社にバレることはありますか?
-
個人アカウントであれば、会社に履歴を確認されてバレる心配はほぼありません。
ただし、EnterpriseやEduプランのアカウントを使っている場合、管理者が会話履歴を取得できる仕組みがあるためバレる可能性があります。
会社にバレて困るプロンプトは個人アカウントで使うのが賢明でしょう。
なお、履歴内容は学習されて別の人に出力される可能性があるため、機密を含む情報やデータを入力するのは個人アカウントでも禁物です。
- SPIや課題に使ったら処分されますか?
-
学校・企業の方針や規約に反すれば、評価取り消しや処分の可能性があります。
学校であれば退学、就職活動では即刻不採用の可能性も考えられるでしょう。
ChatGPTを使っても問題ないかを事前に確認し、ルールを守って利用するようにしてください。
- どのような検出ツールがあるのですか?
-
主に以下のような検出ツールが存在します。
ツール名 特徴 GPTZero AI生成文の検出専用ツール Originality.AI AI生成文検出を含めたチェッカーサービス Turnitin(ターンイットイン) AI検出に対応したコピペ検出システム GPTZeroは無料で試せますが、2025年9月時点では日本語に対応しているとの明確な公式情報はありません。
Originality.AIは日本語に対応しており、ファクトチェックなど多彩なチェックツールも利用できる点が強みです。
Turnitinは個人向けに提供されておらず、主に教育機関や研究機関が利用しています。
- AIを使ったのがバレたら不利になりますか?
-
AIを使ったことが発覚しても、それが直ちに不利になるとは限りません。
AIを禁止する立場もあれば、正しく活用する力を評価する立場もあるからです。
たとえば、出典や根拠を補足しながらレポート作成を効率化するような使い方は、業務改善力としてプラス評価される場合があります。
一方で、丸写しや理解不足のまま提出すると、不正行為や能力不足と判断されてマイナス評価につながるでしょう。
AI利用は「隠せるかどうか」よりも「どのように活用するか」が重要です。
まとめ
本記事では、ChatGPTの使用がバレる理由と対策について解説しました。
最後に、記事の内容をおさらいしておきましょう。
- ChatGPT使用はツールや人の目によってバレる可能性がある
- 実際に処分を受けた事例が教育機関や企業で増加している
- AI文章と疑われる文章には特徴がある
- 適切な書き直しと引用明記でリスクを軽減できる
- 組織のガイドラインに従って利用するのが安全
ChatGPTは作業効率を大幅に向上させる強力なツールですが、規則を守らずに利用するとバレて罰則を受ける可能性があります。
バレても問題のない使い方を実践し、倫理的かつ効果的にAIを活用してみてください。